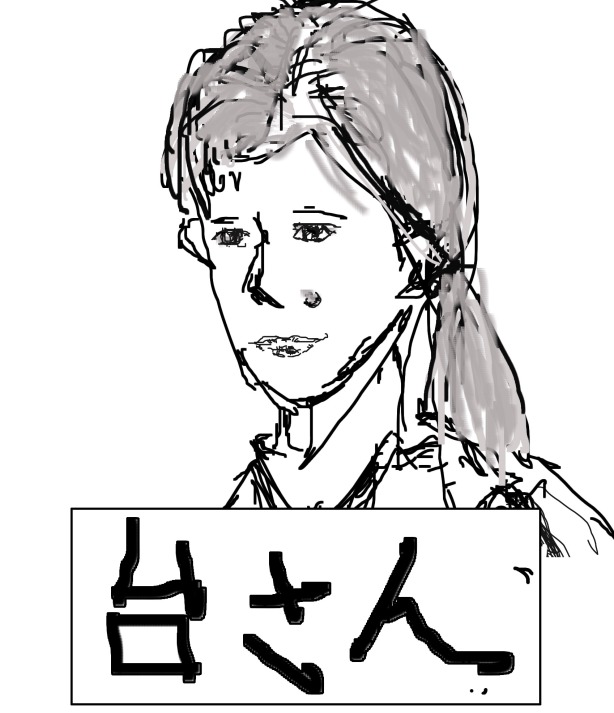論文の構成(目的・対象・方法・結果・考察・結語)
「博士随想」カテゴリーのアーカイブ
歴史学と歴史研究についてのQ&A
名城大学人間学部 伊藤俊一
歴史学って何?
人間社会について、時間による変化の視点からアプローチする学問と言えましょうか。
歴史の研究をするには記憶力が良くないとだめ?
私がこのページを作ったきっかけが、実際に受けたこの質問です。大学入試では記憶力も試しておきたいということで、残念ながら歴史の試験は格好の暗記力検査になっています。しかし歴史の研究が受験勉強の延長のようなことをするというのは大きな誤解です。史料から事実を導いてゆくのが歴史研究であって、むしろ探偵やジャーナリストの作業に近く、コンピュータが普及した今では、ほとんど暗記能力は必要ありません。
歴史学は人間社会の進化の法則を見出すことを目的とする?
これは私は違うと思います。革命は中間層の分解から生じるなどの歴史の展開のパターンについては色々と言うことはできますが、それらは歴史学の結果であって目的ではないと思います(この辺は歴史学者の中でも違う見解があるでしょうが)。
歴史学の本務は、過去に何があったのかを先入見に曇らされずに明らかにするという、「事実」の追及にあると思います。ただ、「1378年に足利義満が花の御所に移った」というのも事実なら、「室町時代の社会」というのも事実です。歴史学にとって前者のような事実を確定する事を「実証」と言い、最も基本的な作業ですが、これらを総合して、後者のような全体的な事実を捉えることも大事な仕事です。
その際に研究者は、自分が現代人として持っている様々な先入見(その社会で一般になっている歴史観など)と格闘しなければなりません。またこの闘いの最大の武器となるが実証でもあるのです。
ただ歴史学が事実を追求する学問だからと言って、社会科学などの理論的仕事に無関心であって良いということではありません。歴史学は他の諸科学に理論の種子を提供し、また理論に啓発されて新しい領域を開拓してきました。
学者の主観によって左右されるため、歴史学は科学ではない?
これは大いに反論したいところです。歴史学は物理法則のような普遍的法則を定立しようとする学問ではないことは確かですが、かといって個々の学者の主観に左右されるものではありません。
歴史学の研究論文で何かを主張しようとする場合、著者は必ず根拠となる史料とその解釈を示さなければなりません。論文を読む人は直接に史料にあたって著者の主張が成り立つかを判断し、多くの検討をくぐりぬけた論文だけが生き残ります。歴史学では、科学の基本である追試可能性が成立するのです。
逆に、これが成り立たない論文は研究論文とは認められません。例えば自分で発見した新史料を使って論文を書いても、他の研究者がその史料にアクセスできないままだと、内容の妥当性が判断できないので、学術的評価の対象にはなりません(歴史畑でない人が歴史的研究を発表する場合、この辺を誤りがちです)。そのため、史料の紹介や公刊というのも大切な仕事になります。
http://toshiito.cside.ne.jp/hist_Q_A.htm
歴史学が科学ならば、自然科学のように進歩する?
これは半分は違います。史料から事実に迫る技術については年々進歩していることは確かです。しかし歴史学は過去のすべての事実を逐一復元することを目的とする学問ではなく、「追求するに値する事実」を選んで研究の対象とします。ある論文の価値を認めるのは同時代の研究者集団であり、史料から正しく事実を導いているかをチェックすることは不変ですが、どんな事実の追求を「意味のあるもの」と判断するかは時代によって変わってくるのです。
それは意識的であれ無意識的であれ、研究者集団が同時代人として、どんな課題に直面しているかというところに影響されます。つまり社会が変わりつづける限り、歴史学も進歩と同時に変化を続けるのです。
何百年も前の事をどうして研究する必要があるのですか?
私の好きな言葉に「時は流れない。それは積み重なる」(サントリーのコマーシャルでショーン・コネリーが言っていたが、出典は不明)というのがあります。ウイスキーでも人間でもそうですが、社会についても、はるかに過去の出来事が現在をしばりつづけていることが多くあります。また今では持っている事を忘れてしまった宝物もあるでしょう。
過去から自由になるためにも、また過去の中から未来への糧を見つけるためにも、社会が変化して行くにしたがって、これまでの道のりの各々の時期を見つめ直す必要があります。
歴史研究の魅力は何なのでしょうか
これは私の個人的感想になりますが、色々な史料を集めて読み込んで行き、その時に本当は何が起きていたのかを追及して行く過程は、なかなかゾクゾクするものがあります(こうして明らかにした個々の事実から、大きな「歴史の流れ」を抽出して論文にまとめて行くのは身を削るようにつらいのですが)。
学者が書いた本を読むのも良いですが、推理小説を読むより、自分が探偵になった方がおもしろいと思いますので、史料を読む事をぜひお勧めします。
それには古文書学などの方法論を身につける必要がありますが、そんなに難しいものではありません。難しいのはむしろ、どこにどんな史料があって、それを見るにはどういう手段を使うか(個人的コネや「業界内での信用」も含む)というような事で、プロの研究者はこのノウハウで食ってきたようなものですが、今後インターネットへの史料の公開が進むと、歴史研究への敷居もどんどん低くなってゆくと思います。
つづく
有些问题,可能几十年都没有人去研究,你要去弄,就发现同时期出来一个人也在弄!
还比你出成果早,当然,这个现象在以前就有人举了无数个例子论证过电话,电灯,飞机等等的发明,都有一个有名的发明家和一个与他之差几天,甚至几小时的无名的发明家在背后。那样的伟大发明都是如此,我只不过是在一次微不足道的事情上亲身体验了一把而已。
一个地区的人群在历史时期里会积淀出自己独特性格。这是自然客观的现象。但同时,人为的调整对其的影响也很大。
日本向来很在意别人如何看自己,最忌讳被人,特别是被外人所笑话。同时也很注意塑造自己的国民性。在昭和初期,整个学界,特别是文学历史方面文化研究者,将日本民族塑造为自古以来崇尚攻势精神,尚武的形象。而战后,对其进行了适度的批判,主要针对战争给日本人民带来了痛苦这方面来说。同时也肯定了其敢于战斗勇于挑战的精神,并用于商业社会。同时根据新的形势,新的时代要求,塑造了爱好和平,友好善良的国民形象。
整个看来日本在每当国内国际形势产生大的变化时候,教育国民适应世界形势,追求自身发展方面,不断调整自己的形象方面是很成功的。本次震灾后,随着世界形势的转变,期待日本形象的再次调整,给世界带来一个新的日本国民形象。同时,我国学界也应努力探寻历史文化中适于现在时期来发扬的东西,将其完善扩大,教育国民,让大家从心里认同并接受,树立中国人的形象。
以下の内容は建築学会公式ネットより転載しています:
東北地方太平洋沖地震災害に対する日本建築学会の行動計画(案)
【原則】
被災者の生活再建と安定のために尽くす
災害事実を記録し、それを情報公開する
災害記録を学術的に分析し、公表する
学術、技術、芸術を総合する学会としての提言、支援を行う
| 1 | 地震・津波による建造物関連の被災状況の詳細な調査、および復旧・復興に関する学術調査を行い、その記録を逐次公開し、最終的に、報告書として刊行する。 |
| 2 | 被災者および基礎自治体の要請に応じて短期の生活再建案の策定および復興計画の策定に学術・研究団体としての中立の立場から支援を行う。 |
| 3 | この災害を、現象(地震、津波、火災、原子力発電所事故)ごと、地理的条件(沿岸・内陸・都市)等の特性との関係でとらえ、防止・軽減に関する研究・技術開発を推進し、必要に応じて、適宜、提言を行う。 |
| 4 | 学術、技術、芸術を総合する学会として、被災した歴史的建造物等の保全・修復・再生に関する研究を推進する。 |
| 5 | 国民全体を被災者と捉え、震災による電力需給逼迫を克服する室内環境、建築環境設備、エネルギー消費、ライフスタイルに関する研究を推進する。 |
| 6 | 被災地の復興に向けて関連学協会、自治体・政府関係機関、NPO・市民組織等との連携を進め、復旧・復興に会員全体で貢献する。 |
5月25 日追加,建筑学会的提携学会,儿童学会组织了灾后重建规划竞赛,很有创意的吸纳儿童青年及成年共同参加,儿童免费,青年便宜,成年收钱也为灾后重建做基金,很有公益性质,全民参与,我们的灾后重建为何不能也多些这样的活动。联想日本最近常做的通过做大型的行为艺术活动,不是一群奇装异服行为怪异的人来侵略某地,而是进行一些很朴素很阳光的理念,尊老爱幼,掘地域文化的精华,促进地区的发展。老少咸宜,群众喜闻乐见的活动,大学生团体,NPO组织和当地人一起来做的,很值得我们借鉴。
另外,附上开头说的竞赛的附加信息,便于了解日本灾情的统计信息
各地区の概要
Wikipedia、役所のHP
地盤沈下調査結果:国土地理院 2011年東北地方太平洋沖地震
http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/h23_tohoku.html
経済・農業・林業・水産業データ:農林水産省
http://www.machimura.maff.go.jp/machi/map/map1.html
国勢調査データ:総務省統計局 都道府県別
http://www.stat.go.jp/index/seido/2-3-5.htm
地域別被害情報(臨海部):社会実情データ図録
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/4362a.html
東日本大震災報告集(英語版有):東北地理学会
http://wwwsoc.nii.ac.jp/tga/disaster/disaster-j.html
津波被災マップ(英語版有):日本地理学会
http://danso.env.nagoya-u.ac.jp/20110311/map/index.html
宮城県震災被害情報:宮城県総務部危機対策課
http://www.pref.miyagi.jp/kinkyu.htm
いわて防災情報ポータル:岩手県災害対策本部
http://www.pref.iwate.jp/~bousai/
福島県被害情報即報:福島県災害対策本部
http://www.pref.fukushima.jp/j/
減災リポートマップ(地図、航空写真):Google
http://weathernews.jp/tohoku_quake2011/map/
その他、今後公表される調査等を積極的に参照してください。
1964年威尼斯宪章 第九条规定了对历史建筑进行维修要将新材料新方法与旧有建筑严格区分开,强调原真性。此法在日后欧美砖石建筑保护维修中作为准则被采用,尽管日本在90年代奈良宪章提出针对木建筑的原真性与砖石不同,将其作为威尼斯宪章的补充而采用,但对欧美主流建筑保存方法的反思则出现在Matthew Hardy主持出版的The Venice Charter Revisited: Modernism, Conservation and Tradition in the 21st Century一论文集中,表达了当代建筑保护业界对将传统与现代对立的保护做法的疑问和在材料和设计手法上更加重视原有建筑的文脉延续。
今天2011年3月毕业本科毕业论文评比结束,过程是昨天论文选考,今天现场发表提问选考。结果评出2人获奖。简单的总结其研究内容,一个是建筑计画方向的,波浪形扶手其实不人体工学,还很危险。一个是建筑史方向的,利休的2榻规模的待庵茶室南墙开窗的照明是利休精心设计的。可见日本本科方面的研究还是比较认真的,所选事物很小但也要研究透彻。另外,两个研究都很注重实验的方法来考察。扶手不用说是要现场考察,连茶室都是学生自己做1:5的模型来模拟照度分布。
建筑史方面的获奖者是重枝老师指导的,重老师本人学部和硕士时都获过此奖,今年参与此评奖的他的另一个学生也一直挺到最后才淘汰。去年指导的一硕士也或此奖。看来还是有两下子。重老师是私指导老师,应该恭喜一下。